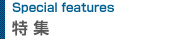不織布新書25春(2)/ユニチカショック/繊維、不織布から撤退/代替品での開発が加速
2025年03月31日 (月曜日)
「ユニチカショック」。昨年11月28日に発表されたユニチカの繊維(ナイロンモノフィラメントやナイロン中空糸など一部を除く)、スパンボンド不織布(SB)、スパンレース不織布(SL)の撤退に伴い、関連企業はその対応に追われている。完全撤退か売却による事業継続かは現段階では不明。しかし、需要家は待ったなし。在庫の積み増しを求める一方で、代替品の開発に取り組む。
〈世界36位の不織布事業〉
撤退するユニチカの繊維・不織布は2025年8月までに事業譲渡先を探し、譲渡先が見つからなければ完全撤退となる。不織布関連ではポリエステルSB、綿100%SL、ポリエステル短繊維などがある。
ポリエステルSB、綿100%SLは国内最大手で不織布の23年度売上高は前期比5・8%減の113億円を誇り、ノンウーブンズ・インダストリー誌によると、世界36位の規模にある。
SBは岡崎事業所(愛知県岡崎市)に年産2万トン、タイ子会社のタイ・ユニチカ・スパンボンド(TUSCO)に1万トンの計3万トンの能力を持ち、SLは垂井工場(岐阜県垂井町)に7千トン、ポリエステル短繊維は1万トンの能力を持つ。
発表後の12月にはユニチカのSBを食品包材に採用する睦化学工業(名古屋市)が「以前よりBCPの観点から同品質の不織布を準備しており、供給面でご迷惑をお掛けすることはありません」とホームページ上で公表するなど、既に対策を打った企業もある。
国内外の同業他社もユニチカの商権を狙った開発や提案が始まっている。ただ、「問い合わせはあるものの、価格的に合わない」という声もある。
〈わたは特殊品種が多い〉
一方で、不織布の代替以上に難度が高いのがポリエステル短繊維など原料の代替だ。ユニチカからポリエステル短繊維やナイロン短繊維の供給を受ける短繊維不織布メーカー向けは別注の専用品種など特殊品が少なくない。そこにユニチカの強みがあったのだが…。
ポリエステル短繊維の構造改革は年産3万トンから1万トンへの縮小を発表した14年度以来。当時も貼付基布用のサイド・バイ・サイドわた「C81」の撤退などで需要家は代替対応に追われたが、現在、専用品種の供給を受ける、ある短繊維不織布メーカーは「26年9月まで生産すると聞いているが、日々状況が変化している。人員の問題もあって、希望した量を確保できるか分からない」と懸念を示し、なくなる前提で代替品による開発に着手するが「試作費用は自腹」。ポリエステル短繊維などを購入する短繊維不織布メーカーの大半がこうした対応を余儀なくされている。
また、代替品でユニチカ品と同じ物性を出せるかどうかも課題だ。短繊維不織布は原料により機能性や物性を確保する部分も大きく、原料変更は需要家の認証を受けなければならない業界もある。
それだけに短繊維不織布メーカーの技術開発力が試されているとも言え「25年はユニチカ対応に追われる一年になる」(短繊維不織布メーカー)との声も上がる。試作開発費もかかるため、さらなるコスト上昇も懸念される。
〈大手の構造改革相次ぐ〉
24年はクラレ、東洋紡、ユニチカ、それに先立つ23年10月は三井化学と旭化成の大手SB2社による合弁会社設立やSB最大手の東レの生産規模最適化など繊維素材メーカー大手の規模縮小、撤退、売却など構造改革が相次いでいる。公表されていないが、今も水面下でさまざまな動きがあり、予断を許さない。
ただ、業界再編は繊維や不織布だけではない。ご破算になったが、ホンダと日産自動車など「あらゆる産業界で起こっている」とある短繊維不織布メーカーのトップ。そして「不織布も衣料用繊維と同じになる可能性は高い。設備投資や人材確保の問題から中小にも構造改革が波及する恐れもある」と危惧する。
その中で、不織布業界で圧倒的に多い中小メーカーはどう生き残るのか。「価値が認められなければ撤退するしかない。付加価値が取れるニッチな市場に向かうためにも、技術開発力を高めるしかない」と指摘する。