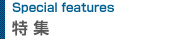ジーンズ別冊25SS(7)/デニム関連有力企業に聞く/日本デリバリーサービス/ドアーズ/INAHO Manufacturing.,Ltd(旧グロワール)/コトセン
2025年03月28日 (金曜日)
〈日本デリバリーサービス 社長 二畠 大 氏/海外向け販売に良い兆し〉
2025年6月期上半期(24年7~12月)売上高は前年同期比横ばいでした。下半期は、梅春向け商品を出荷する1月はそれなりの受注量を獲得しましたが、2~3月は低調でした。通期目標を売上高16億円に定めていますが、前期比横ばいの約15億円になりそうです。
国内向け販売は、実質賃金の低下などの影響で、勢いに欠けます。新型コロナウイルス禍の下での消費低迷ほどではありませんが、需要回復にはまだ時間がかかりそうです。
一方で、海外向けは良い兆候が表れています。海外ブランドからの引き合いが増えているほか、インバウンド需要を狙い日本製を求める国内メーカーからの受注も増えつつあります。ハンドクラフト(手擦り)で加工したジーンズやセルビッヂデニムといった海外顧客から高い評価を得る日本の技術を足掛かりに需要を捉えていきたいです。
ただし、海外のメゾンから企画の早さを求められるようになってきたことで、地の利に勝るイタリアの生産者が台頭しています。米国のトランプ大統領が打ち出す保護主義で、今後世界がどのように変わっていくか予測できません。今後の動向を慎重に見極めます。
このほど、備後産地のデニム関連事業者の若手を中心としたグループ「デニムのイトグチ」が主催する産地若手交流会「ワープ&ウエフト」の工場見学会で、参加者に自社工場を案内しました。
工場見学の実施は、中途採用した人材を育成するため、同交流会への参加を推奨したことがきっかけです。人手や後継者が不足する影響で、産地は目に見えて衰退しています。交流会を通じて地域の繊維産業に対する帰属意識を高め、人手不足を解消していきたい。併せて、残業抑制などの取り組みで、働きやすい環境づくりも進めていきます。
〈ドアーズ 社長 鳥谷 泰嗣 氏/メード・イン・ジャパン絶やさない〉
2024年9月に東京・代官山で合同展示会「デニム・クリエーション・サーカス」を初開催しました。当社の呼びかけに応えてくれた11社が参加、アパレルはもちろん、染色や縫製、洗い加工、付属までの工程を公開するもので、会期の3日間、一般を含む多数の来場をいただきました。
当社は1998年設立のOEM/ODMを主力とするデニムメーカーです。完全国内生産と企画力を強みに取引先を増やし、22年は過去最高の売上となりました。翌23年、創業社長からバトンを継ぎ、社長に就任しました。
ジーンズの人気はインバウンドを追い風に高まっていますが、国内物価の上昇が続き、消費は右肩上がりとはいえません。
さらに、モノづくりの現場はコスト高騰や人材不足といった課題が深刻化しています。
このままでは、業界が培ってきた技術と品質、ジーンズが好きでこの世界に入ってきた若い世代の情熱を維持できなくなってしまうのではないか。そんな危機感がありました。
これを打破するため、ジーンズ生産に関わる企業が一堂に集まり、都心で開催する企画を考えました。川上から川下までが国産ジーンズの力強い流れと可能性を発信できないか。当社の呼びかけに、予想以上にたくさんの人が共感してくれました。
展示会名の「サーカス」は、クリエイターの力でワクワクする空間を、製品を作り出そう、という決意表明でもあります。今回の取り組みによって、アイキャッチになる新しいプロダクトも生まれ、内容の濃い展示会となりました。
デニム・クリエーション・サーカスは今後も続けていく計画です。異業種の企業がチームとして市場の活性化に継続して取り組み、新たな推進力になることを目指します。
〈INAHO Manufacturing.,Ltd(旧グロワール) 社長 戸田 聡一郎 氏/社名変更で新たな門出〉
当社は4月1日をもって会社名を「グロワール」から「INAHO Manufacturing.,Ltd」(イナホ・マニュファクチュアリング・エルティディ)に変更します。将来的に年間売上高160億円の達成を目指しており、その実現のために進めているリブランディングの一環です。ディレクターの原田大士氏を顧問に迎え、社名のみならず、さまざまな面で会社に変化を加えていきます。
その第一歩となるのが、4月から岡山県倉敷市児島で稼働する新たな縫製工場「フラッグシップファクトリー」です。ライン編成の自由度を高める仕切りのない空間で光源を一定に保ち、仕様書表示用のつり下げディスプレーを設置するなど、効率を突き詰めた設計となっています。
工場設備というハードの構築と併せて、ソフト面も一新します。コンシェルジュのように均一なサービスを提供できるソフトウエア「ライブファクトリー」を開発しています。生産管理の過程を効率化しアパレルや商社の生産管理担当者にかかる負担を軽減できます。
縫製工場が抱える一番の問題といえる人手不足を解消することで、強固な生産基盤を確立します。
インドネシアのバンドンにある日本語学校の隣に縫製工場を設け、今後始まる育成就労制度で来日する人材の縫製練度を事前に高めます。当社が育成した人材の協力工場への就労も後押しし、在留資格の「特定技能1号」を取得後は、協力工場間での転職も可能な柔軟なキャリアプランを形成します。
日本人の縫製オペレーターの確保も模索します。日本製を商品のストーリーとして発信したい顧客へ映像や写真を付加価値として提供することで、縫製加工料以外の収益を得て給与を増やし、人材確保につなげます。
〈コトセン 社長 渡邉 将史 氏/海外展でモノ作り伝える〉
上半期(2024年9月~25年2月)は微増収となりました。セルビッヂデニムの加工は落ちもせず、ずっと堅調に入ってきている一方、広幅のデニムは悪いです。定番品はあまり動いておらず、特殊な生地が増えている印象です。
当社は先月、フランス・パリで開かれた繊維総合見本市、「プルミエール・ヴィジョン(PV)・パリ」に出展しました。デニム製造の篠原テキスタイル(広島県福山市)、ロープ染色の坂本デニム(同)と協力し、経済産業省中国経済産業局のブース内で「デニムユニオンジャパン」としてPRしました。当社の名前を出して海外展へ出展するのは初めてのことでした。
同展では、クラボウの裁断片などを独自の開繊・反毛技術で再資源化する「ループラス」を採用した生地や、ループラスの生地に顔料コーティングを施したもの、当社が持つ6種類の加工表現を発信しました。特に6種類の加工表現では、同じ生地を使用していても加工によってこれだけ種類があるということを訴求しました。顔料コーティング生地も人気があるなど、生地もある程度ピックアップがありました。
ブースでは国内におけるデニムの生産工程について来場者に伝えたほか、岡山県織物染色工業協同組合が展開する、独自の安全基準に沿った加工ブランド「倉敷染」のパンフレットもおいてアピールしました。
日本のモノ作りを見える化していくことは大切だと思います。日本製のモノを売るために、整理加工という工程も根拠になってきます。実商売につながるまでは遠いかもしれませんが、今後も日本のモノ作りの評価につながっていくのであれば出展していきたいです。
下半期に向けては、加工のバリエーションを見直しながら顧客へ提案を強化していきます。自分たちがやっている価値を再認識していこうと考えています。また、設備更新も必要になってきます。