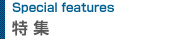ボーケン品質評価機構/機能性事業本部/機能性を“見える化”
2025年03月25日 (火曜日)
ボーケン品質評価機構(ボーケン)の六つの事業本部の中で、「機能性」に特化した業務を担う機能性事業本部。製品価値を向上させる「機能性」を“見える化”するためにさまざまな評価方法・評価基準も開発してきた。現在、「加工剤から材料、製品へと一貫した機能性評価機関」「機能性能の品質と表示のプロフェッショナルへ」「繊維製品だけではない、日用消費品にも対応する機能性評価機関」へと進化することに取り組む。
〈原料から製品まで一貫評価/ユニチカガーメンテックと提携〉
ボーケンはこれまでも納品前の機能性試験も含めて、原料・生地・加工剤について多くの評価方法を持つ。その範囲は吸水速乾性や吸湿発熱など快適に焦点を当てた機能、抗菌防臭性や抗ウイルス性など清潔に焦点を当てた機能、帯電防止や防炎性など安全に焦点を当てた機能など幅広い。
こうした実績に加えて、最終製品の性能評価や体感に関する評価にも対応するため、サーマルマネキン計測器による試験や生理測定で豊富な実績があるユニチカガーメンテック(UGT)との業務提携を強化している。両社が協業することで加工剤から原料、製品へと一貫した機能性評価が可能だ。こうした取り組みを通じて、依頼企業や業界のニーズに合わせた新たな評価技術の開発も進めた。
例えば要望が高まっている暑熱対策商品の機能性評価方法として気化冷却性試験、クーリング性試験、持続冷感性試験などを開発している。UGTと協業することで体感を加味した評価基準の設定と試験が可能だ。疲労回復パジャマや遠赤外線効果による血行促進作用のある衣服などリカバリーウエアの性能評価でもボーケンとUGTが連携することで素材の機能評価と生理測定による人体評価を実現した。
〈加工評価を可視化/衛生や環境でも存在感〉
近年、日常生活で目に見える課題を解決するための機能加工が多く登場している。その一つが、水回りに発生する“ぬめり”汚れ。細菌がバイオフィルムを形成したものだ。これに対して抗菌製品技術協議会(SIAA)が中心となり、ボーケンも参画してプラスチックなどを対象とした抗バイオフィルム性試験を開発した。現在、国際標準規格(ISO)にもなっており、ボーケンでも試験を実施している。
ボーケンは2024年に化粧品汚れに対する防汚性評価法を開発した。機能の数値化やサーモグラフィなどを用いた試験や評価も多く実施しており、機能を可視化することで消費者に分かりやすく訴求できる評価方法を提案している。
やはり目に見えない細菌やウイルスを対象とした衛生や、リサイクル繊維の判別など環境に関する分野の試験でも存在感が高まる。
既に豊富な実績を持つ抗菌性や抗ウイルス性の試験に加えて、花粉・ダニ・ペットなどに由来するアレルギーの原因物質である特定タンパク質に対する低減加工の試験を実施している。
また、4月から繊維評価技術協議会の「SEKマーク」の認証もスタートし、ボーケンは指定検査機関として2月から試験の受付を開始している。
特定タンパク質低減加工の評価方法にはISO4333があるが、使用する試薬の関係などから納期が長期化し、試験手数料も高額になるという課題がある。これに対してボーケンは花粉とダニ由来特定タンパク質を対象とした低減加工評価の定性試験(加工効果の有無を簡易的に判定する試験)を「BQEC009」として開発しており、低価格・短納期での評価も実現している。
リサイクル繊維や環境配慮設計など環境関連の標準化が活発化する中、リサイクル繊維の判別にも取り組む。既にペットボトル由来リサイクルポリエステルの判別は提携するSGSでの委託で実施しているが、さらに自社で保有するMALDI―TOF質量分析計を使用した再生ポリエステルの鑑別技術の開発に着手した。
分析機器を開発した島津製作所との共同研究を実施している。繊維to繊維リサイクル繊維の判別、バージン原料とリサイクル原料の混合率算出などこれまでない技術に挑戦する。25年度中には定性試験の受付開始を目指す。
〈“専門人財”多士済々〉
機能性事業本部は、多様な専門人財をそろえることで“顔の見える”試験機関となることを打ち出している。
大阪機能性試験センターの小出真也所長は繊維鑑別・混用率試験などを中心に品質試験業務への従事を経て新規試験方法の開発にも取り組み、混用率試験のJISやISO制定にも参画した経歴を持つ。吸水ショーツなどフェムテック製品の評価方法と人工血液の開発も担当した。現在は大阪機能性試験センターを所長としてけん引するとともにリサイクル繊維の判別技術などの開発も進めている。
東京機能性試験センターの太田智子所長代理は機能性試験全般を担当し、プラスチック引布など繊維外の分野でもISO提案など標準化活動に参画する。東京機能性試験センターが試験所・校正機関に対する国際規格であるISO17025を取得する際の中心メンバーであり、気化冷却性試験やジェル製品の持続冷感性試験、化粧品汚れに対する防汚性試験など新規試験の開発も担った。
若手も活躍する。大阪機能性試験センターの森田和孝主任は持続冷感性など暑熱対策の機能性試験など快適性を評価する試験方法を開発した。素材評価と製品評価を結びつけることをテーマに衣服内環境やフェムテック製品の評価方法の開発を進めている。講師を務めた機能性試験セミナーでは機能性を体験できる装置を開発し、分かりやすい情報提供を日々実践する。
〈品質と表示のプロ集団に/非衣料分野にも対応拡大〉
機能性繊維製品にとって機能の評価と並んで重要になるのが表示問題だ。ウェルビーイングの実現のためには機能性を客観的に評価し、消費者の期待を裏切らない表示が不可欠となる。この際、問題になるのが景品表示法や医薬品医療機器等法など法規制に抵触しないように配慮しながら消費者に訴求することだ。
ボーケンは機能性の評価に加え、法規制への抵触を避ける試験方法と試験結果に基づいた表示について提案するなどサポートを行っている。顧客の品質を担保するために新機能の評価基準の提供も行う。新たに開発した評価試験については目安値の設定を顧客に提供することで、機能の差の確認やどのような表示が可能なのかを提示するなどする。
繊維製品分野で培った試験技術を生かし、試験対象をプラスチック製品、建材、寝具・寝装品、日用消費品など非衣料分野にも拡大している。衣料品は人体に最も近い領域で使用する製品のためさまざまな機能性試験方法が実用化されてきた。衣料分野発祥の機能や評価方法は非衣料分野でも有効だ。
ボーケンは機能性評価の総合試験機関として対象分野を拡大し、日用消費品などに対する評価も実施する。例えば、傘の遮熱性や床材の特定タンパク質低減加工、薬剤の抗菌性、靴のムレ感の評価などがある。
〈積極的な情報発信/試験開発や高度化も〉
機能性に関する最新トレンドや業界情報に関して試験機関ならではの知見を生かした情報発信も積極的に実施する。セミナーの開催に加え、外部の展示会などにも積極的に出展し、業界全体での知識向上に貢献することを目指している。機能や試験方法の有効性を体験できるブース作成や実演を交えたプレゼンテーションなどへの評価は高い。
また、機能性試験の精度を高めるための技術開発や試験開発の高度化にも力を入れている。
例えば吸水ショーツの吸水量や防汚性の評価に使用する人工血液を開発し、特許も出願した。通常の血液とは異なる粘度を持つ経血を模擬することで、高精度な評価が可能になる。その他、試料生地の長期耐久性を評価する方法でも特許を出願した。試料生地の上質感がどの程度長持ちするかを評価するもので、学生服のテカリ、白化、長期しわなど従来の物理的強度だけでは評価できなかった生地表情・上質感の耐久性を評価できる。
〈理事 機能性事業本部長 吉岡 陽一郎 氏/専門家集団として取り組む〉
当機構は4月から「中期経営計画2027」をスタートさせます。新中計では事業ビジョンと組織ビジョンを掲げており、機能性事業本部は機能性能の品質と表示に関する専門家集団として地に足を付けて取り組みます。
依頼企業との関係をしっかりと構築できる人財も育成し、対象分野の拡大とサービスの拡充、深さの追求を行いながら、社会・業界の課題を解決する機能性評価機関としての役割を担うことを目指します。(談)