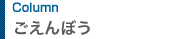ごえんぼう
2025年03月24日 (月曜日)
日本に「織」の付く地名がたくさんあるのに対し、「編」は苫編(兵庫県姫路市)か靱編(大分県日田市)など、数えるほどしかない。やはり「編み」の歴史が浅いからか▼『日本メリヤス史』(藤本昌義著)によれば、ニットは戦国時代に伝来し、江戸後期になると武士の内職として天竺編みのメリヤス生産が人気となる。足袋や肌着などが作られ、日本人は手先が器用なのか、海外製の機械編みに比べ遜色のない物を作る武士もいたらしい▼幕末には刀の柄を覆う「柄袋」の素材としてメリヤスが大流行。しかし、165年前の今日、その流行が終わる。季節外れの雪が降る江戸城外で大老の井伊直弼が暗殺された。いわゆる桜田門外の変だ▼護衛の家臣がメリヤスの柄袋だったことでとっさに刀が抜けず、暗殺を防げなかったといわれる。歴史に「もし」は禁句だが、ニットでなければ……。歴史の転換点の陰にニットがあるのは面白い。