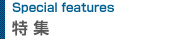特集 アジアの繊維産業(8)/インドネシア/価値創造で“脱・価格競争”/現地や海外市場で成長へ
2025年03月19日 (水曜日)
インドネシアの日系繊維メーカーが進化の時を迎えている。これまでは汎用(はんよう)素材の量産を担ってきた日系工場は、現地の製造コストアップや安価な中国製品の席巻で、高付加価値素材の開発や新たな商流の創出を迫られている。日本の衣料品市場が低迷する今、インドネシアでの“地産地消”や中東、ASEANなど“第三国”に伸び代を求める企業が増えている。
〈25年も5%台の成長見込む〉
インドネシア経済は2020年、世界的な感染症の流行により1998年のアジア通貨危機以来、初めてGDPでマイナス成長となった。しかし、翌2021年にはプラスに転じ22~24年は5%台を維持、国際通貨基金(IMF)は今年も5%台の成長を予想している。
ただ、国の経済成長とは裏腹に、ここ数年、日系繊維企業は難しいかじ取りを迫られている。今年2~3月にかけて、オンラインで複数の日系繊維企業に近況を聞いたところ、主力の日本市場向けの商材は苦戦が続いており、現地、欧米市場でも汎用的な素材の売れ行きは極めて低調だ。この2年間でインドネシア内に非常に安価な中国製の糸・生地、縫製品が流通するようになっていることがその原因だ。
現地の大手繊維メーカーでも、中国企業による繊維素材や縫製品の“捨て売り”“投げ売り”、密輸にシェアを奪われ、24年は廃業、倒産が相次いだ。こうした事態を受け、インドネシア政府は同年8月、セーフガードを発動したが、目立った効果は得られていないもよう。
今月、現地大手繊維メーカー、スリテックスが破産、1万人超の従業員が解雇された。この背景にも、中国品の安売り攻勢があるといわれている。「政府も中国品流入を止められない。日本企業は商材や商流の根本的な見直しを迫られている。安い中国品を利用してビジネスを構築したり、中華系と組んで一緒に成長するぐらいの戦略が必要」と現地のある日系商社の代表は語る。
〈中東の生地輸出など有望〉
中国品の流入でシェアを奪われる分野がある一方で、好調が続く商権やこれから有望な市場もある。その一つが中東民族衣装や宗教用衣装だ。東レ、蝶理、シキボウ、東洋紡の各現地法人はこの分野での売り上げを近年、順調に拡大させており、今年も成長を予測する。「中東圏に限らず、中東からアフリカへと再輸出される商材もあり、まだ旺盛な需要がある」(日系商社)
世界第4位の人口を誇るインドネシア国内市場や米国、ASEAN諸国への生地輸出も成長が期待できる。こうした分野では、いかに日系企業ならではの新たな価値を素材に乗せ、中国や現地メーカーとの価格競争から脱出することが鍵となる。
既に汎用素材とは異なる高付加価値素材の開発に着手している日系メーカー、商社は多い。機能性のあるわたを現地で調達し、現地で生地にして、縫製も行い現地市場で販売するという商流も出始めている。「当社の素材で縫製までする“地産地消”の需要は増えている」(東レグループ)
最近では、欧米市場で欠かせない“環境”という付加価値に焦点を当てた商材開発や中華系メーカーでは難しい少量生産対応を日本企業の強みとして打ち出す企業も出ている。
ある繊維メーカートップは「日本市場が縮小に向かう中、現状のビジネスモデルでは成長は難しい」としながらも「インドネシアも厳しいとはいえ、人口ボーナス期であり、出生率も高い。幅広い分野で長期的に成長が確実な“拡大が約束された市場”だ。やり方次第で成長することは十分可能だ」と話す。
〈スポーツ衣料に商機/東洋紡グループ〉
インドネシアの東洋紡グループは現地や海外市場における、素材や縫製品の販路開拓に力を入れる。同グループの繊維事業は、これまで日本市場へのニット地販売を主力としてきたが近年、現地スポーツ衣料などで日系繊維メーカーの機能素材の需要が拡大しつつある。
同グループを統括する、東洋紡インドネシア(TID)の現地での生地、縫製品の販売数量は今期(2025年3月期)大幅に増える見込みだ。TIDの松村修社長は「今期の現地での販売量は前期比1・5倍、来期も同等の伸びを計画している」と話す。近年、ドレスシャツ、ランニング、ヨガ、テニスといったスポーツウエア市場で同社のニット地の採用実績が増えており、今後もこうしたアイテムを手掛ける現地アパレル向けの需要増を予想する。
主力の日本向けでは、現地で調達可能な商材のバリエーション拡大に取り組む。主要取引先である親会社、東洋紡せんいに向けて、機能性わた、糸、生地の調達を現地でできるようにし、コスト競争力を磨くことで、東洋紡の繊維事業全体の利益率アップに貢献する。
インドネシアの東洋紡グループは生地輸出・内販、商社機能を担うTID、生地の編み立て・染色加工の東洋紡マニュファクチャリング・インドネシア(TMI)、縫製工場のシンコウ・トウヨウボウ・ガーメント(STG)の3社で構成する。
〈“環境”の取り組み充実/日清紡グループ〉
日清紡グループは、インドネシア内での紡績、織布、加工の一貫生産体制を強みに、新商材を開発し、現地や日本以外の海外市場への販売を強化する。同グループのインドネシア法人は、紡績・織布のニカワテキスタイル、織布・染色加工の日清紡インドネシア、縫製のナイガイシャツインドネシアの3社。主力は、日本で流通するユニフォーム・シャツ用の生地。
“環境”に関する取り組みに力を入れることで、環境関連の要求が高い市場に向けた素材の供給拡大を狙う。既に原綿(綿花)調達では、生産国を選別し、国際認証の取得した素材を充実させ、原料までさかのぼれる明確なトレーサビリティーを確保している。
工場のエネルギーの使い方も工夫することで“環境”を考えた工場としての素材の付加価値向上につなげている。同グループでは2017年からボイラーの燃料に石炭とバイオマス燃料との併用を開始、現在、バイオマス燃料比率は25%に上る。
ニカワテキスタイルでは21年に石炭自家発電設備を停止し、全量を国営電力からの購入に切り替えたことで、エネルギー由来の温室効果ガス排出量を60%削減した。
22年半ばからはインドネシアグループ3社の電力を地熱発電による再生可能エネルギーに切り替え、スコープ2(買電)の温室効果ガス排出量ゼロを達成している。今後、排水の再利用による水使用量削減やバイオガスの活用などにも取り組む。
〈シキボウのメルテックス/生産設備強みに開発加速〉
シキボウのインドネシア紡織加工会社、メルテックスは、自社の紡績、織布、加工設備を生かして高付加価値素材(糸・生地)の開発を加速させる。少量生産対応や同社ならではの機能、付加価値で違いを生み数量増や新規顧客開拓に取り組む。日本、中国、台湾、ベトナム、タイにあるシキボウグループ企業と製造、販売での連携も強める。
同社の主力はポリエステル・綿混の糸・生地で、用途は中東民族衣装用と企業ユニフォーム・シャツ用の2本柱。同じグループの製織・染色加工場、シキボウ江南(愛知県江南市)で仕上げを行うケースが多く、メルテックスの現在の売上高のおよそ8割が日本向け輸出となっている。
今期(2025年12月期)は増収増益を計画する。中東民族衣装向けの素材の販売で好調が続くほか、これまで低調だった定番ユニフォーム地の需要に回復の兆しがあると言う。そこに伸び悩みが続く紡績事業をテコ入れすることで全社的な業容拡大を狙う。
メルテックスならではの独自性のある糸の開発力に加え、大規模な工場にはできない少量生産対応や環境やリサイクル分野の国際認証も生かして糸の生産・販売量の増加につなげる。「紡績設備は老朽化が進んでいるため、ニーズや市況に合った設備投資も検討する」(小川英良社長)
〈蝶理インドネシア/リサイクル繊維の調達・供給増へ〉
蝶理のインドネシア法人、蝶理インドネシアは、リサイクル繊維の調達・供給力を強める。廃棄ペットボトル由来の再生ポリエステル糸や廃棄衣料から作る産業資材などの需要が欧州、日系企業で高まっており、今後も長期的な成長を見込む。
欧州や日本市場で、環境を考えたリサイクル素材の需要は年々拡大しており、最近ではインドネシアのローカル市場でもニーズが出始めているそうだ。こうした状況で、素材メーカーの一部では、生産効率と品質を追い求めるあまり、再生ポリエステルを作るために新たなペットボトルを作り、すぐに破砕して再生ポリエステル原料にするという、逆に環境負荷を重くする素材も出ている。
こうした中、蝶理インドネシアは、「エコブルー」という再生ポリエステルブランドを展開する日系メーカーという信用力を強みに、本来の再生ポリエステルの意図に沿った素材の現地での調達力、供給力を強化し糸、生地、資材などさまざまな用途での供給拡大を目指す。
生地輸出事業では蝶理とウラセ(福井県鯖江市)などと合弁で設立した現地の染工場、ウラセプリマを活用した新たな生地の開発と新規の取引先開拓を加速させる。従来のブラックフォーマル、白衣、ユニフォーム用生地に加え、メンズや単色無地染めの生地開発にも力を入れ、欧州市場でも売り先を探す。
〈24年度営業利益3倍/東海染工のTTI〉
東海染工グループのトーカイ・テクスプリント・インドネシア(TTI)の2024年12月期決算は、売上高が18%増、営業利益が前期比3倍になった。石炭、ガス、水などの単価下落、省エネ・節水の徹底、さらに生地加工の段取り改善が利益躍進に貢献した。
同社は織物・ニットの漂白、染色、プリント加工を主力とし、独自に生地の企画・販売も行う。売り上げの6割はインドネシア国内の需要によるもので、残りは米国、ASEANなどへの輸出による。現地の日系企業で珍しく親会社への取引がない独立した経営形態だ。
新型コロナウイルス禍前は綿素材に絞って加工していたが、20年以降、ポリエステル・綿混、レーヨン、テンセル混など加工素材の幅を広げ、前期は新規顧客への企画提案を強化し数量が増えた。
今期も受注量を増やす。既存顧客からの受注を維持しつつ、新たなターゲットとなるインドネシアアパレルからの受注増、米国、ASEANへの輸出拡大に力を入れる。ポリエステル100%の生地加工もできるようプリント後の蒸しや洗い工程で設備投資を検討している。
インドネシアの断食月に例年、受注が不安定になるため、こうした宗教行事の影響がない国での受注量増で稼働の平準化を図る。直近の加工数量は月産350万~400万ヤードでフル稼働が続いている。