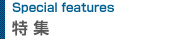特集 アジアの繊維産業(4)/東レの東南アジア戦略/地殻変動を好機に/高まる開発・マーケティング機能
2025年03月19日 (水曜日)
東レの東南アジア繊維事業の姿が大きく変わろうとしている。タイ、インドネシア、マレーシアの各グループ会社が連携し、生産品種の高付加価値が加速したことで、開発・マーケティング機能が一段と高まった。米国の通商政策変更によって繊維のサプライチェーンも地殻変動が起こる可能性がある。こうした変化を好機とするためにもサプライチェーン最適化を推進する。
東南アジアの繊維市況は2024年も厳しい環境が続いた。糸・わた・生地いずれも安価な中国品の流入が続いており、特に汎用(はんよう)品・定番品の競争が激化している。このため操業停止や経営破綻するローカル企業も出てきた。東レグループ各社も影響は避けられず、定番の糸・わたやポリエステル・綿混織物などの拡販に苦戦している。
一方、これまで力を入れてきた生産品種高度化の成果は確実に上がっている。例えば、世界的に要望が高まる環境配慮型素材としてリサイクル繊維ブランド「&+」(アンドプラス)のポリエステル繊維はタイ、インドネシア、マレーシアで生産と供給が可能になっており、販売量も拡大した。スポーツ向け長繊維織物やカジュアル衣料向けの風合い加工生地なども新規開拓が進む。
生産品種高度化に向けた設備投資も実施した。タイでは複合紡糸設備の導入が進められており、産業資材分野でも自動車用原糸・基布の生産・品質管理のデジタル化を進めることで競争力が高まった。
25年も繊維産業を取り巻く環境は大きく変わるかもしれない。最大の変数は、米トランプ大統領が中国などへの関税引き上げを宣言するなど通商政策の変更だろう。繊維のサプライチェーンにも地殻変動が起こる可能性があり、“脱・中国”の動きが加速する。これが東南アジア地域の東レグループ各社にとって新たなビジネスチャンスをもたらすかもしれない。
衣料から産業資材まで、グローバルなサプライチェーンの再編に適応し、アジア地域における繊維素材・製品の開発・供給・マーケティング拠点としての存在感を高めることが、東レの東南アジア各社の目指す役割となる。
〈東レ インドネシア/グループ連携で開発加速/“地産地消”の需要開拓へ〉
インドネシア東レグループの2025年3月期売上高は前期比減収となりそうだ。中国からASEANへと安価な繊維、繊維製品が流入しており、ポリエステル綿混素材などで苦戦を強いられている。ただ、利益はコスト削減などに取り組み、増益を目指す。同グループは、今後も中国品が市場を席巻するとみて、ポリエステル・綿混素材を主力とするグループ会社の構造改革を推進する方針。
中国や現地の安価な繊維素材(糸・生地、縫製品)に対抗するため、グループ間の連携を強め、新たな商材開発を加速させるとともに品質や機能を重視する売り先や新市場の開拓が今後の課題となる。本稿では同グループの主要メーカーの現状と今後の戦略をレポートする。
ポリエステル・ナイロン合繊糸・製造・販売のITSは、汎用(はんよう)品とは異なる機能や原料などで付加価値化した商材での成長を模索する。今後の市況について「安価な中国品の流入で厳しい状況は変わらない」としつつも、インドネシア一貫で繊維素材を調達するニーズは広がるとみて、グループ一貫での新商材開発やサプライチェーンの拡大に向けた検討を進めている。
同社は直近の商況について「ポリエステル短繊維は昨年より商況は若干改善に向かっているが、予断を許さない状況。フィラメント関連は今後、厳しさが増す」と予想し「市場の回復には期待せず、従来通り商品の高度化を進め、インドネシア一貫のサプライチェーンの構築・拡大を強化していく」方針を示す。
ポリエステル・綿混織物製造・販売のCENTEXは、定番シャツ地市場で、中国製の生地が流入したため苦戦、今期の売上高は20%減収となる見込み。「ポリエステル・綿混シャツ地の需要はかなり減少し、既存サプライヤーおよびその顧客が大苦戦となった」
今後、グループ会社と連携した商品の高度化とインドネシア縫製での縫製品再輸出への取り組みを強化する。同国内で生地調達、縫製される“地産地消”への顧客要望の高まりが背景にある。
コスト削減策としてグループのETXに織布工程を集約するなどして生産の合理化を図る。「(米国による)関税率引き上げがコスト上昇要因となり、ひいては作り手に支払うコストを下げようとする圧力につながる。こうした“下げ圧”を跳ね返すに足る顧客目線での付加価値を実現することが大きな課題となる」
ポリエステル・綿混紡績、織布のETXの今期業績は減収減益となりそうだ。主力のシャツ、ユニフォーム地で苦戦、堅調だった中東も市況が鈍化しており、今期も大きな回復は見込めない状況だ。
こうした中、グループとの連携を強化し、新商品開発、生産供給体制の最適化を進める方針。グループ外の顧客や新規用途の開拓も行い、グループ内外でバランスの取れた成長を目指す。
コスト面では生産体制の変更や生産性向上による固定費削減、継続した原単位改善活動による比例費削減などにより自社競争力のさらなる強化を図る。
ポリエステル・レーヨン混紡糸・織布・染色加工のISTEMは今期、販売数量は前期並みを維持し、品質やコスト競争が過熱するも、業績は前年比増収増益の見通し。今後、「(これまで堅調が続く)アフリカ学童ユニフォーム市場や中東民族衣装市場は、中国と韓国のサプライヤーとの競争がさらに厳しくなる」と予想し「優良顧客との取り組み強化と品質保証体制の整備で、当社の品質、ブランド力を強みにさらにシェア拡大を図る」方針。
アクリル梳毛紡績と糸染めのACTEMの25年3月期決算は、染め糸の輸出拡大とコスト削減により増収増益の見通し。来期、インドネシアでの糸の染色からニット製品までの一貫サプライチェーン構築によるコストメリットを訴求し、日本市場の新規開拓を目指す。
ISTEM、ACTEMともに生産管理の高度化や作業効率の改善による生産性向上、要員削減などのコスト削減に取り組む。これから太陽光発電設備導入による用役費削減の検討を始める。
TIINの繊維事業は、大都市圏でのアパレル販売の成長率が鈍化しつつあるが、今後も富裕層向けの需要は引き続き堅調に伸びると想定する。こうした中で、「中間層の市場拡大、中規模都市での需要拡大がどのように進むか注視が必要」とし、一方で「生産拠点としてのインドネシアの重要性はさらに増しており、当社はグループの生産拠点を強みとした業容拡大を目指す」としている。
〈在インドネシア国東レ代表 トーレ・インダストリーズ・インドネシア 社長 梅木 英雄 氏/製販、商流で進化遂げる〉
インドネシアの近年の対ドル為替、外貨準備高、株価や金利、貿易収支、インフレ率といった経済指標はこれといった不安材料は少なく安定した成長が続いています。2024年の同国の実質GDP成長率も5%台を維持しました。ただ、景気の指標となる同国内自動車販売台数(24年)はこれまでの回復基調から一転、前年比1割以上の減少に転じ、二輪車販売台数の伸び率もかつてよりも鈍化しました。
こうした中、当社の売上高の大半を占める繊維事業はここ数年、厳しい状況が続いています。その大きな要因は、中国からの非常に安価な繊維素材の流入です。24年にはインドネシア大手繊維企業の中でも中国品にシェアを奪われ、操業停止や倒産も相次ぎました。
この難しい局面を打開するために当社では、安い商材とは一線を画す、高品質や新たな価値を持つ商材の開発、販売を加速させる方針です。自助努力でコスト競争力を磨くとともに、当社ならではの素材が求められる新たな市場開拓も欠かせません。日本、中国、ASEANに展開する東レグループとの連携や相乗効果が期待できる取り組みにも力を入れていきます。