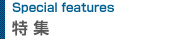特集 北陸産地(2)/北陸との取り組み強化/蝶理/東レ/旭化成アドバンス
2024年12月24日 (火曜日)
〈蝶理/テキスタイル重点拡大/産地との取引は250億円へ〉
蝶理は北陸産地との取引額を前期の230億円から今期(2025年3月期)は240億円、来期(26年3月期)は250億円に拡大する計画だ。25年は顧客との関係をさらに深めながら取引額を伸ばす考えで、「糸の供給だけでなく、生地の仕入れも重点的に伸ばしていく」(芦田尚彦常務執行役員繊維本部長)とする。
北陸との取引拡大などを狙いに、今期は各素材のブランディング強化に注力してきた。戦略商材に位置付ける再生ポリエステル「エコブルー」、高伸縮糸「テックスブリッド」、ピン仮撚り糸「SPX」などの認知度を高めながら北陸品の出口を増やしていく狙いで、北陸製生地を使った製品展開に注力するとともに、戦略素材の川下や一般消費者に向けたマーケティングを強化している。
独自のブランド糸をテキスタイル、製品につないで展開していく方向の中、近年は特に糸と製品で順調に伸びている。今後に向けては「製品での認知度が上がっているが、テキスタイルでより広げる必要がある」とし、素材事業部と製品事業部の双方でマーケットイン型の素材開発を強化していく。
例えばテックスブリッドは、製品展開が前期の27万着から今期は42万着に伸び、生地が85万㍍から96万㍍に拡大する見通しだが、生地の伸び幅が小さい。今後は糸、生地、製品の全てをバランスよく伸ばしていく考えで、重点的に拡大するテキスタイルは年率20%の成長を狙う。
産地の生産基盤維持に向けた設備投資も検討していく。SPXでは来年に協力工場へピン仮撚り機を導入することを決めているが、そのほかの分野でも設備投資を検討していく。
〈東レ/高付加価値化進む/実感できる機能性など重視〉
東レは、引き続き北陸産地を商品作りにおける重要なパートナーと位置付ける。20周年を迎えた東レ合繊クラスターの活動を中心に、今後も産地との取り組みを深めていく考え。
テキスタイル事業部門の2024年の商況は堅調に推移する。ファッション、スポーツ、ユニフォーム、輸出の各分野とも高付加価値化が大きく進んでいることから、前年比では大幅な増収増益を達成できる見通しだと言う。
産地企業との取り組み品で特に好調な商品、今後期待できる商品では、独自の複合紡糸技術「ナノデザイン」を使った差別化商品や、「ボディシェルEX」「ドットエアー」「サマーシールド」などの盛夏対応商品を挙げる。「キューダスXT」などPFAS規制対応撥水(はっすい)品にも注力する。
25年の市場環境は、国内、中国、米国、欧州ともに厳しいとみる。その中でも「消費者にその良さがはっきりと分かる差別化された機能性を持つ素材にはニーズが必ずある」として拡販に注力する。25年のテキスタイル開発では、「実感できる機能性」「猛暑対策」「サステイナブル」を重要なキーワードに位置付けている。
北陸産地との取り組みは、「それぞれが勝てる領域に集中」しながら深化させる。産地の技術を活用した海外展開にも注力する考えで、「ブランド政策、しっかりした機密保持や適正なコミッションが前提だが、大いに可能性あり。一部は既に進行している」とする。
〈旭化成アドバンス/アウトドア用順調に拡大/ベンベルグ裏地も貢献〉
旭化成アドバンスの繊維事業は今期(2025年3月期)、衣料用途が順調に伸び、資材用途も安定して推移する。アウトドアなどがけん引し、下半期(24年10月~25年3月)の北陸産地との取引量は上半期より拡大する見通しだ。
衣料用途は、学販など調整局面を迎える分野もあるが、アウトドアの薄地織物が順調に伸びているほか、ファッションアウターや民族衣装、裏地なども堅調に推移する。アウトドアは欧米市場での在庫調整が一巡し、国内向けも堅調を維持。PFAS(有機フッ素化合物)規制をにらんだ非フッ素系への切り替え前の備蓄用特需もあり、順調に伸びている。
ファッションアウターでは、ベンベルグ使いやジアセテート使いなどが拡大している。裏地はベンベルグ以外の素材に一服感が出ているものの、ベンベルグ使いの需要は安定して推移する。旭化成からの「ベンベルグ」裏地の生地製造販売事業の移管が、12月から業績に寄与することもあり、今期は拡大を見込む。
衣料が伸び、資材用途が安定していることから、今期は2桁%の拡大を狙う。25年の市場環境は慎重にみているが、各分野での取り組みを維持・拡大しながら、輸出を伸ばすための取り組みを強化する。
衣料ではベンベルグ裏地の輸出を改めて掘り起こすほか、資材は旭化成の商材、独自の商材とも海外を伸ばす。
来年4月に稼働させる現地法人を生かしてインド市場での拡大も狙う。インド法人は車輌資材からスタートするが、さまざまなアイテムを販売できる形にしており、衣料用途での需要も探る。
〈合繊メーカー/繊維事業の再編が続く〉
2024年は合繊メーカーの繊維事業からの撤退が続き、産地を取り巻く事業環境の変化をうかがわせる年となった。近年は収益性を重視した一部事業からの撤退も進んでおり、25年の動向が注視される。
この数年で合繊メーカーの事業撤退が急速に進んだ。三菱ケミカルグループは、23年にアクリル短繊維「ボンネル」の生産・販売を停止し、今年9月にはトリアセテート繊維事業をGSIクレオスに売却することを発表した。
11月はユニチカが官民ファンドの支援を受けるとともに繊維事業から撤退することを発表した。衣料繊維、不織布、一部を除く産業繊維について来年8月までに売却先を探し、見つからない場合は1年ほどを経て撤退するもよう。
繊維事業の縮小・撤退は合繊以外でも急速に進んでいる。22年には日東紡が紡績事業から撤退しており、23年には東洋紡が国内の紡績工場と染色加工場を統合・集約するなど構造改革が加速している。
事業ごとの見直しも各社が進めている。東レは収益が低迷しているポリプロピレンスパンボンド不織布(PPSB)やポリエステル短繊維の生産適正化を推進しており、既に韓国子会社でPPSBの製造ラインとポリエステル短繊維の連続重合・直接紡糸(連重)設備を一部停止した。今後、愛媛工場(愛媛県松前町)の連重設備も停止する予定だ。
構造改革を加速させた要因の一つが新型コロナウイルス禍による供給・物流制約で、ウクライナ紛争などに端を発する世界的なインフレ高進も大きい。原燃料価格の高騰が続き、物流費や人件費の恒常的上昇が重なる。価格転嫁が進まない商品は即座に採算性を失う。市場では国内市況悪化に直面した中国メーカーによる安値攻勢もあり、日本の繊維企業は採算性が悪化した分野の抜本的対策に迫られる。
こうした環境の変化を受けて、日本の繊維素材メーカーのキーワードになっているのが「勝てる領域」で、25年も事業の見直しが進む可能性がある。