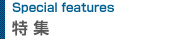特集 北陸産地(1)/事業環境が大きく変化/24年は震災から激動続く
2024年12月24日 (火曜日)
〈将来に向け新たな動きも〉
北陸産地の2024年は年明けから不透明感が増し、春、夏と弱含みで推移した。足元はまだら模様の中で、秋ごろからは回復の兆しが出始めた分野もあるが、市場環境は全体として厳しい状況が続いている。25年に向けては、底打ちして回復に向かうとみられる用途がある一方、人材確保難やサプライチェーンの脆弱化、産地を取り巻く事業環境の変化など対応すべき課題も多くなりそうだ。
24年は元日に能登半島大地震があり、石川県の七尾市や中能登町、宝達志水町、内灘町など繊維関連の企業が多い地域も被害を受けた。被災した企業は復旧作業に追われることになり、一部では廃業も見られた。
地震によるサプライチェーン混乱への対応が重要課題になり、産地内連携も進めながら、困難な時期を乗り越えていった。復旧に動いた企業の多くは、春までには再稼働にこぎ着けたが、建屋の修繕など完全復旧には時間がかかり、被害が大きい企業の中には25年に持ち越すところもある。企業の廃業への対応も、フライシャトル織機など一部では新しい形での組み立てがまだ完了していない領域も見られる。
1月は被災によって生産が停滞したが、需要も全体として弱含み、春から夏にかけて産地の景況感は厳しさを増していった。欧州アウトドアやユニフォームなど流通在庫の増大を受けて調整局面を迎えた用途があり、自動車メーカーの不正問題などの影響も見られた。足元の稼働は大きく落とさないものの受注残がどんどん減っていき、スペースが空きだす工程も出てきた。
〈生産量は減少傾向〉
北陸3県の24年1~9月の織物生産は、3億1987万平方メートルで前年比6・8%減となった。石川県は1月が前年比22・1%減と震災の影響で大きく減少。2月は2%減にとどめたものの、3~6月は2桁%の減少が続いた。7月は前年比増となったが、8月と9月は再び前年比減になり、厳しい市況感を表す数字となった。
一方、福井県は被災した工場が少なかったが、1~6月は前年同期比数%の減少で推移。7月と9月は前年比増となり、回復に向かっている。ただ、秋からは中国向けを含めてファッション用途の減速も見られ、先の不透明感が増した。
10~12月は、欧州の景況減速や流通在庫増大の影響があったスポーツ・アウトドア、在庫調整局面にあったユニフォーム、自動車メーカーの不正問題の影響があった車輌などに回復が見られる。堅調なSPA向けなども下支えし、明るい話が段々と出てきた。
ただ、暖冬や中国市場の失速などの影響があるファッションは国内外とも弱いまま。インテリア、インナーなどにも回復が見られず、好調だった中東民族衣装用もブラックでは減速感が出ている。
用途ごとに景況感が異なるまだら模様の状態だが、全体としては厳しい状態が続いている。人件費を含むコストの上昇や、サステイナブル化や認証取得などの環境コスト、人手の確保難などの課題も引き続きあり、25年の市場環境は慎重にみる声が多い。
〈ボトルネック顕在化〉
糸加工から染色加工まで全ての機能がそろい、それぞれの技術を組み合わせた高付加価値化ができることが産地の強みの一つだが、24年はボトルネックがさらに顕在化した年でもあった。
特に染工場のスペース不足による納期の課題が浮上したほか、撚糸などの工程もタイトに推移した。震災の影響が残る時はサイジングなどもボトルネックとなった。
ただ、ボトルネックとされる工程でもスペースが空く時期もあり、持続可能な産地機能の在り方が改めて注目される年となった。
合繊メーカーの再編が進んだことも大きなトピックスだった。9月に三菱ケミカルがトリアセテート繊維「ソアロン」をGSIクレオスに売却して繊維事業から撤退することを発表したのに続き、11月にはユニチカが繊維事業からの撤退を決めた。
ソアロンは世界唯一の素材であり、ユニチカも同社ならではの商品を持つ。ユニチカの影響は売却先がどうなるかなど現時点で見えにくい部分が多いが、特徴ある素材を持つ2社の決定はインパクトが大きく、産地を取り巻く事業環境が変わっていくことを明確に表す事例となった。ただ、産地からは「繊維事業から撤退したからといってマーケット自体がなくなるわけではない」との声も聞かれ、新しい形への対応が重視されている。
その一方で産地の新しい形に向けた動きも進んだ1年で、カジグループの織布新工場「カジファクトリーパーク」(石川県かほく市)が稼働し、丸編みのマルゲンや広部撚糸が新工場建設に動くなど将来を見据えた投資も出てきた。蝶理のピン仮撚り機への設備投資など産地との関係が深い大手企業も動きだし、事業継続や産地の基盤維持に向けての動きが出てきている。