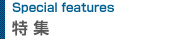特集 環境ビジネス(11)/進展を見せる各社の環境への取り組み/カケン/ケケン/ボーケン
2024年12月17日 (火曜日)
〈LCA関連サービス強化/繊維の環境負荷低減支援/カケン〉
カケンテストセンター(カケン)は、ライフサイクルアセスメント(LCA)に関するサービスの提供に力を入れている。関連する展示会への出展やセミナー開催などを通じて訴求を続けており、実施件数や問い合わせが増えてきた。サステナビリティ経営推進室は「繊維産業の環境負荷低減の一助になりたい」と話す。
LCAは、製品やサービスにおける資源採掘から製造、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体の環境影響を定量的に評価する手法。温室効果ガス(GHG)排出量だけでなく、酸性化や資源消費などのさまざまな環境影響について評価できる。「ISO14040」シリーズで標準化されている。
カケンでは、LCAの算定代行、伴走型の算定コンサルティング、クラウド版LCA算定支援ソフトウエア「MiLCA」(みるか)の販売などを行っている。建築や物流、自動車関連企業からの問い合わせは多いが、関心を示す繊維関連企業が増えてきたと言う。
繊維関連企業との取り組みでは、子供服製造・販売と連携。子供服は、お下がりされることも多いが、「一着の服を1人で着用した場合とお下がりで2人が着用した場合では二酸化炭素(CO2)の排出量が違う」とし、連携した会社の製品でCO2排出量の削減率を可視化した。
伴走型コンサルティングの話も増えている。コンサルティングでは毎月定例で打ち合わせを行い、相談・助言の機会を設けている。「繊維は環境負荷の大きい産業といわれている。LCAに関連する支援を通じて、環境負荷低減に取り組んでいる企業を支援したい」と語った。
〈TEの浸透に注力/特定技能で注目高まる/ケケン〉
ケケン試験認証センター(ケケン)は、人権や環境保全などに配慮している倫理的(エシカル)な繊維製品を認証するテキスタイル・エクスチェンジ(TE)の浸透に継続して力を入れている。TEの認証件数は着実に増えているが、特定技能1号で人権が重視される中、さらに注目度が高まる可能性がある。
ケケンによるTEの認証件数は増加傾向を示す。2024年4~9月期は目標として掲げた3・5倍には届かないものの、前年の2・5倍に拡大し、浸透を見せる。けん引役となっているのが、最終製品に含まれる原材料のうちリサイクル成分5%以上が基準の「RCS」(リサイクル・クレーム・スタンダード)だった。
今後は、RCSに加え、「GRS」(グローバル・リサイクルド・スタンダード)の伸長にも期待をかける。GRSはリサイクル成分の含有率の基準が高くなるほか、化学品規制などが含まれ、認証取得はより難しくなる。ただ、人権(従業員の労働体系)などにも関連することから問い合わせが増えていると言う。
人権対応への関心が高まっているのは、海外企業との商売拡大に加え、特定技能1号にも不可欠であるからだ。TE認証は、RCSとGRSを軸に増やしていきたい考えで、前年比3・5倍という目標を取り上げることなく、前向きに進む。
「環境ラベルの自己宣言」の支援にも力を入れる。自社で基準を設定し、それを満たすことで環境への配慮を示すのが自己宣言で、「ISO14021」でルール化されている。グリーンウオッシュにつながらないよう、ケケンが宣言を検証する仕組みを作る。
〈ZDHCの第三者検証機関/独ゴーブルーと業務提携/ボーケン〉
ボーケン品質評価機構(ボーケン)は、繊維・皮革産業の有害化学物質排出ゼロを目指す非営利団体、ZDHCの化学物質在庫表の第三者検証機関の役割を担っている。今年8月、ZDHC認定ソリューションプロバイダーの一つであるドイツのゴーブルーと提携した。
ZDHCのプログラムに参加する企業は、製造時制限化学物質リスト(ZDHC MRSL)に適合するように化学物質を調達、使用、排出しなければならない。調達と使用の具体的データはZDHC認定ソリューションプロバイダーのアプリケーションに登録して適合性を判断し、パフォーマンス・インチェック(PIC)リポートが発行される。PICリポートの在庫表にある化学物質が実際に施設に存在するかを第三者検証機関が監査し、適正に保管・使用されていると判断すればインチェック適合マークを発行する。ボーケンは2023年からZDHCのインチェック監査の第三者検証機関になっている。
一方、ゴーブルーは、ZDHC認定の化学物質管理アプリケーション「BHive」を提供する。ZDHCメンバーのナイキやプーマ、メンバー以外でもZDHC MRSLを導入しているギャップなどがBHiveを採用している。ゴーブルーのマネージングディレクターであるラース・ドゥーマー氏は「繊維産業向けに開発された点が強み」と話す。
今回、ゴーブルーと提携したことでボーケンはBHive採用企業のインチェック監査をワンストップで実施することができる。業務を担当する認証・分析事業本部の木村英司本部長は「これまでも他の業務提携先のシステムを使った監査を実施してきたが、BHiveが加わり、さらに幅広いニーズに対応できるようになった」と話す。