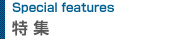秋季総合特集Ⅱ(2)/対談 在庫が繊維の未来を変える/フルカイテン 代表取締役 瀬川 直寛 氏/shoichi 代表取締役CEO 山本 昌一 氏
2024年10月22日 (火曜日)
近年、在庫の持ち方が変わりつつある。以前は「在庫=悪」という考え方が強かったが、市場が縮小する中、成長のためにはいかに適正な在庫を持ち、適時に供給できるかが鍵を握るようになってきた。さらにSDGs(持続可能な開発目標)や環境配慮に沿ったビジネスの在り方が求められる中、在庫の処分についても、単に廃棄するわけにはいかなくなってきた。そういった在庫の在り方に着眼し、ここ数年で成長してきたのが小売業の在庫管理・分析を支援するフルカイテン(大阪市福島区)と在庫処分サービスを展開するshoichi(同中央区)だ。その両トップ、フルカイテンの瀬川直寛代表取締役とshoichiの山本昌一代表取締役CEOに、在庫に対する認識の変化とこれからを語ってもらった。(Zoom/ウェブ会議ツールで対談)
〈分析・予測の技術構築から〉
――会社の事業を紹介してください。
瀬川直寛氏(以下敬称略) 2012年5月にベビー服のEC(電子商取引)販売を始めたのですが、在庫を抱え過ぎて3回も倒産しかけました。この倒産危機を乗り越えていく時に、適正な在庫で売り上げや粗利益(売上総利益)をアップさせていくため、在庫分析や予測の技術を開発しました。それをフルカイテンとして事業化し、ビジネスとしてやり始めたのが17年になります。大学卒業後の10年間、IT系でキャリアを積んできたことがあり、私自身がAI(人工知能)や統計を研究していたことがバックグラウンドにあります。
当社はいろいろな企業が抱えている在庫を上手に売り上げや利益に変える、在庫の分析予測のサービスを提供しています。4年前の調査で、抱えたSKU(商品の最小管理単位)の最大でも2割ぐらいの中から、粗利益の8割が生まれているという、“パレードの法則”そのままの結果が出ました。言い換えれば残り8割のSKUが利益へ貢献をしていないということになります。
取れるはずの利益をいっぱい毀損(きそん)している。ちゃんと利益を取れるような分析予測のサービスを提供し、在庫問題を解決するのが当社の仕事となります。
山本昌一氏(同)最初は学生の頃に、フリーマーケットで仕入れた服をヤフーオークションで売っていました。1億円くらいは売り上げていました。05年に大学を卒業し普通に働くよりも、起業してつぶれるまでやってみようと。そしたら、つぶれずにここまで来れたという感じですね(笑)。
しかし、卒業から2年ほどたつと、中古の売買に大手資本が少しずつ入り始め、やりにくくなってきました。そんな時、あるフリーマーケットで有名ブランドを売っている人に出会ったんです。6万円のパンツを5千円で売っていて、なぜそんなに安いのか聞くと、コネクションがあるからと。ちょっと話を聞かせてくれと居酒屋に連れていき、2時間ほど話を聞きました。これは面白い、一生涯のビジネスとしてやろうと決めたのが、その時でした。
ただ、こういうビジネスは家族経営が多く、事務所の固定費を抑えて電話1本で物事を進める代わりに、商品を保有する力は弱かった。そこで当社は処分する服を加工する、倉庫を借りる、従業員を雇って仕分けする、B品も買い取るという逆張りをしたんです。そして、すぐ買い取りますから売ってくださいという営業をかけました。最初は勝ったり、負けたりでしたが、いつからかshoichiに頼んだ方が早いという認識がされるようになってきました。
同業者は、あまりこのビジネスを息子や娘に承継しようと考えていません。自分の商売を格好良いと思っていないからだと思うんです。でも僕はこの仕事が大好きで、子供にもぜひ承継させたい。だから設備投資をものすごくしています。同じ業界の中でもだいぶ差が開きつつあります。
――フルカイテンも立ち上げ当初の苦労はありましたか。
瀬川 起業してすぐに驚くような有名企業から問い合わせが来て商談が決まるなど、営業面での苦労はありませんでした。だけどやっぱり、システム面の苦労はありまして、全店舗のSKUのデータや入荷などを高速に処理して、AIに学習させるシステムの改良が22年まで続きました。
データが重すぎて、予測結果を見たくてもすぐに見られない状況でした。契約してもらっても使えず、めちゃくちゃ怒られて解約されるということもありました。ビッグデータの計算に費やしながら何とか生きながらえてきました。そこは他社にまねできず、競争優位性があると思います。現在アパレルで200ブランドとの取引があります。
山本 毎年100~200社取引が増えていまして、今まで4千社ぐらいとの取引があります。忘れたころに電話がかかってくるというケースも多いですね。多分、この業態としては日本で最高のシェアを確保していると思います。
〈二極化する企業〉
――近年、小売りの在庫の持ち方や量にどのような変化や傾向が見られるでしょうか。
山本 在庫の持ち方として無茶苦茶タイトになってきています。有名なブランドであれば、在庫量が残り1%、多くても2、3%ぐらいになっています。通販はまだ多いと思いますが、値段で勝負する企業が多く、いっぱい作る必要がある。思想的に売ってから作るのは楽ですが、結局キャンセルや売り逃しの発生もあって難しい。
しかし、全体的に在庫は減っています。一つの品番を売り切ったら、増産せずに新しい商品を作るケースが増えています。前は旧正月前に秋冬物を追加で発注するケースもありましたが、今はほとんど聞かない。
瀬川 在庫は新型コロナウイルス禍をきっかけに減らそうとしてきました。そういう企業は一定の割合でいますが、われわれから見ていると、逆に在庫を増やしているという企業が昨年ぐらいから増え始め、それらの企業の中でも二極化が起こっています。
業績を上方修正し、ぐいぐい伸ばす企業もあれば、在庫を積まないと売り上げが立たないという企業もいて、当然後者の方が苦戦しています。値引きばかりでコロナ禍前と同じように利益が取れなくなってきた企業も増えています。全体を見ると、先ほど山本さんがおっしゃったように極力適量でいこうというメンタルが生まれていると思います。
――適正な在庫回転率とかあるのでしょうか。
瀬川 業界では4~5%ぐらいが多いのではないでしょうか。それよりは適正な粗利益率で消化させていく感じでしょうか。ただ、消化率だけを意識するといくらでも値引いても良いことになってしまう。プロパー消化率という言葉もありますが、それを追いかけすぎると、消化が進まなかったりするので、適正な粗利益率を意識しながら、どうするかというのが大事だと思われます。
そういう点ではGMROI(商品投下資本粗利益率)という指標の話を最近は耳にする機会が増えています。どれだけ少ない在庫で粗利益を稼いだかという指標です。プロパー消化率も結局粗利益につながる話になります。そこを稼げないと何も投資できなくなります。
山本 在庫処分する時って、決算が黒字の時か、銀行に言われた時になりますよね。あとは物流費を抑えたい時か。要はバランスだと思います。売り上げは単価×品番×1品番当たりの販売数という法則なので、企業の成長のためには単価を上げるか、品番を増やすか、1品番当たりの販売数を増やすしかありません。
あと、在庫処分の際、誰の責任かというのが企業によって違いますよね。企画かMDの責任か、結構そこは違いを感じます。
日本の企業の場合、責任の所在がなくて、決算の時に役員が在庫を処分するかどうか判断するケースが多い。ある意味、平和な世界ですね(笑)。
瀬川 確かに在庫責任を負っている人はあいまいなケースが多い。年に何回か、社長が決算前に在庫をこれだけ減らせという号令がかかり、そういう在庫がshoichiさんのところへ行くのでしょうね(笑)。
毎年、「在庫を減らせ」という圧力があれば、在庫を減らした方が良いと思ってしまう。ただ、単純に減らせば当然売り上げは落ちて、それはそれで怒られる。だから、在庫って簡単に減らすことも難しいんです。
〈売れない商品は一定数出る〉
――日本における大量生産、大量消費の時代は終わったといわれます。次に訪れるファッション消費におけるキーワードは何だと考えますか。
瀬川 大量生産、大量廃棄というところから適量生産、適量消費の時代に行くというのは、私の持論というより皆さんそう思われており、サプライチェーン全体が適量化に向かっていくはずです。
山本 SDGsや環境配慮はこの先もずっと続くと思います。ところが、消費者がそのあたりを意識して購入するかと言えば、微妙なところです。そればかりを追求するようになると、商品も面白くなくなってしまう。その中でバランスをどうとるかだと思います。
――環境配慮の意識が強まれば、在庫を作らないという流れも強まっていきます。在庫処分サービスへの影響もいずれ出てくる可能性は?
山本 正直、今のところ分かりません。自社の戦略としてはシェアを取っていくしかないと考えています。あるブランドがよく売れれば、その商品を多く作らなければいけない。でも急にぱったり売れなくなることもある。そういう“波”は、フルカイテンさんのサポートを受けていたとしてもなかなか読むのが難しい。
アパレルってもうかる時はもうかるのですが、もうからない時は本当にもうからない。もうけられる時にもうけないと、後がしんどくなる。
――別注、オーダーメード需要が増えています。在庫の持ち方も変わってきそうですか。
瀬川 当社では一部別注のビジネスもサポートしていますが、結局裏側の生産背景の話になります。あるアパレルメーカーは4週間でMDを回しており、そういう裏側の強みを作るために投資されてきたんだと思います。
だから、短納期で作り、売り切れごめんというスタイルを築いている。他社と比べて在庫の効率はすごく良いですが、そこまでやっても、先ほど山本さんが話されていたように、売れない商品はかなり一定の割合で出てきます。
冒頭にお話ししたパレードの法則がありますが、その2割が4割になることはあっても、5、6割になることは想像できないんですよ。5、6割にしたい場合は、生産背景を変えないといけない。これは簡単なことではなく、やはり5割超えてくるのは難しいと思います。
〈インフラの立場で〉
――アパレル在庫の適正化は、繊維業界にどのような未来をもたらすでしょうか。
山本 結局、環境への貢献と適正利益でしょうね。それしかないでしょうか。
瀬川 その通りですね。そしてその先です。営業利益率が3%や4%となり、適正な利益が稼げるようになりましたと。そういうことがちゃんと投資に回るということだと思います。ブランド力を高めるためにも何かしらの投資が必要です。店舗、商品、スタッフというのはブランドを感じる瞬間にもなります。いかに特別な体験を提供できるかというのもブランド力強化の一つのポイントであり、より高収益な事業に変わっていけます。
今、ファッション業界を見ていると店舗のスタッフの数が少なくなっています。この前商談した企業も8人から6人体制にするとおしゃっていて、そうなると人時生産性を高める必要があります。人数が減ったので、店舗売り上げが落ちましたのでは意味がありません。
山本 海外SPAの店舗では最近、店員が少なく、サイズがなければネットから発注してくれというような感じになっています。ああいう形態の店が今後どんどん増えていくのかなと思います。店で働くのが格好いいというイメージがなくなってきたのが残念ですよね。でもある程度夢がないと面白くない。
フルカイテンさんみたいなアパレルに横串を刺していくインフラのような企業が今後求められてくると思います。shoichiもそういうところでポジションをとっていきたい。インフラというポジションを崩さず、自分の会社を成長させていければと思っています。
〈海外へも活路開く〉
――これからのミッションやビジョンをお聞かせください。
山本 7月9~11日にイタリアで開かれた国際服地見本市「ミラノ・ウニカ」(MU)に初めて出展しました。日本でシェアは取れていますので、後は海外をやるしかないという感じです。やっぱり僕は日本が好きなので、日本勢が海外市場を攻めるというのは余力があれば絶対やっていくべきでしょう。やらない理由はなくはないですか?
――MUでは何か手応えをつかみましたか。
山本 著名ブラントと名刺交換ができ、いろいろと話しができました。まだ、ビジネスにつながるかどうか分かりませんが、とにかく2年間は海外の展示会に出ようと考えています。
欧州連合(EU)では来年から売れ残った衣料品の廃棄を禁止する法律が施行される予定で、話を進めている段階にあります。今、業者を選定している段階にあり、この2年間でビジネスが構築できなければ、その後に何回行っても一緒だと思います。当社のようなビジネスモデルを構築している企業はなかなかないと思いますので、心が刺されば十分可能性があると思います。
瀬川 提供しているサービスが今四つありますが、これを来年ぐらいに倍ぐらいに増やそうとしています。全部、抱えている在庫からもっと売り上げ、粗利益が取れるようにしようというものです。それぐらい予測や分析が入る余地って在庫にはまだまだあります。
こういうことをやりながら、導入企業のデータを毎日蓄積していっています。今1兆5千億円分ぐらいの流通総額になるデータが蓄積されています。このデータを使い、小売業全体の特徴を見いだすような予測につなげていこうと考えています。データをどう料理し、価値を提供できるかという、データサイエンス領域の基礎研究も続けており、このあたりを形にしていくのが当社のビジョンとなります。それができれば必要な商品を必要な量だけ流通するという、あるべき社会へちょっとでも近づくのではないかと考えています。
――フルカイテンのようなビジネスモデルは海外でも出てきていますか。
瀬川 あまり聞きませんね。競合するのは大体お客さんが社内で使われているエクセルなんですよ(笑)。今は外資系ブランドの日本法人と何社か契約があります。まず、日本で成果を出して、そのチャネルで本国へアプローチをしていこうと考えています。
――両社は在庫予測と在庫処分の両極にありますが、将来的には連携したビジネスもあり得るのでは。
瀬川 当社が取引している企業は、全部shoichiさんと契約していると思うんですよね。
山本 いや、そんなことはありません(笑)。フルカイテンさんのビジネスは在庫を残さないサービスなので、弊社と連携していてはダメですよ。
瀬川 ブランド価値の毀損を気にし過ぎてshoichiさんのようなサービスを敬遠する企業もあります。正直、それは良くない。本当に毀損するかもしれませんが、会社をつぶすよりも良くないですかと思うんです。バランスシートを奇麗にして、改めてブランド価値を高めるために、投資していく方が正しい判断だと思います。
期中に売る努力をしていても、それでもリードタイムが短くない以上、どうしても構造的に在庫が残る。shoichiさんのようなサービスを活用し、次の投資にその資金を生かす、そういうことも在庫の健全なサイクル、サーキュラーエコノミーの一つだと思います。
――どうもありがとうございました。